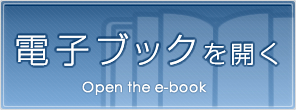097号 page 30/212
このページは 097号 の電子ブックに掲載されている30ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
20 高知論叢 第97号されている3。しかし,日本の代表的なコモンズとされる入会草地の放牧利用を想起するとき,排除ができるかどうかは必ずしも財・サービスの性質を決定する主要な要因とは言えそうにない。入会慣行....
20 高知論叢 第97号されている3。しかし,日本の代表的なコモンズとされる入会草地の放牧利用を想起するとき,排除ができるかどうかは必ずしも財・サービスの性質を決定する主要な要因とは言えそうにない。入会慣行のもとでは,入会地を管理する組織が形成されており,放牧地を柵や土塁で囲った上で駄番などの呼称をもつ草地の監視員の常駐制度させている場合が少なくない。このとき,牧柵は牛の管理がもっぱら目的とされており,域外者の排除は副次的である。しかも,現代日本の草地利用における最大の問題は,草地の過剰利用ではなく,過少利用なのである。過少利用が問題になっている限り,利用者を排除する必要性は低下する。また,過少利用は当該資源が維持できなくなるという産業的な視点だけでなく,人為による攪乱が二次的な自然を生み出し,希少種となった動植物の生育環境が失われるという生物多様性の視点からも問題視されるようになっている。そこで,本稿ではコモンズと呼ばれてきた資源の中で,排除可能性だけからは把握しきれない資源に着目し,その形成過程を検討することを課題とした。この形成原理の解明は排除可能性から整理できるコモンズを含めたより広いコモンズの理解を促すばかりでなく,過少利用という現代的な課題をコモンズ論の中で解釈する枠組みを提供しうる。以下,第2 節では日本の草地を事例に,共同利用の形成過程を簡潔に整理した上で,過少利用問題がどのように発生しているかを述べる。第3 節では,排除可能性ではなく,資源の生産性を人為的に改良できるかどうかに着目し,コモンズの新しい分類を試みる。第4 節では,人為的なストックの有無がいかにコモンズの現代的な課題のあり方を規定しているかを検討する。最終節では,結論を述べる。2.草地における共同利用の展開と過少利用問題の発生(1)共同利用の形成以下では,筆者がフィールドとしてきた三瓶地域における草地(以下,三瓶3 Hardin[13].