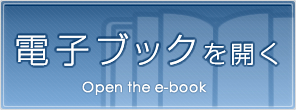097号 page 53/212
このページは 097号 の電子ブックに掲載されている53ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
海のコモンズの現代的可能性43(2) 漁業テリトリーの形成と資源系の囲い込みコスト 日本民俗学の高桑〔25〕は,「ムラ-ハマ-イソ-オキ-オクウミ(ヤマナシ)」(ムラ,ハマはオカ,イソ以降はウミ)という漁民....
海のコモンズの現代的可能性43(2) 漁業テリトリーの形成と資源系の囲い込みコスト 日本民俗学の高桑〔25〕は,「ムラ-ハマ-イソ-オキ-オクウミ(ヤマナシ)」(ムラ,ハマはオカ,イソ以降はウミ)という漁民の空間認識に対応させる形で,「ムラ-ハマ-チサキ(地先)・磯漁場-オキ(沖)・沖合漁場(入会)-オクウミ(ヤマナシ)」という形で漁場を区分し,陸地での村境の先を海にのばした線によって囲われ(距離は地域によって異なる),それぞれの村によって占有される地先漁場と,その外に広がり,入会として誰が利用してもよい沖合漁場の二つの利用形態の異なる海域があるとしている(註6)。このような慣行は一村占用漁場慣行と呼ばれる(浜本〔3〕, p. 20)。このような地先/ 磯場と沖の区分は,近世には既に全国でおこなわれ,中世にも既に同様の区分が存在したことが指摘されている(白水〔22〕, p. 34)(註7)。また,この一村占用漁場慣行は,現在の第一種共同漁業権の原型となっている(浜本〔3〕, p. 20)。 一村占用漁場慣行は江戸時代に確立したと言われている。この慣行は,地域によって様々な違いはあったにしろ,「磯は地付き,沖は入会」,すなわち船の櫂が海底に届く沿岸部は地元の漁村が独占して利用し(地付き), それより沖合は自由操業(入会い)が許され独占利用できないという原則として理解されている(浜本〔3〕, p. 20)。このような慣行は近世には広く存在したと考えられており,18世紀には幕府の法令(この場合,漁場の相論をめぐる幕府の裁定原則)として文書に残されている(『律令要略』(寛保2(1742)年)所載の「山野海川入会」)(註8)。 しかしこの原則は,地先水面の境界を具体的に示すものではなく,「沖合と地先との境界は,その海村の慣行に委ねられていた」ため,しばしば境界をめぐって様々な紛争が発生した(片岡〔12〕, p. 50)。上記の原則も,実は中世以来村々で漁場をめぐり様々なトラブルが起こり相論/ 争論を通じてそれを解決していく過程で生まれてきたと考えられる。 海という空間は, その性質上具体的な境界線を海面上に引くことが困難であり, 山アテなどの手段で自らの位置を確認する他はない(註9)。また, 境界の「史料的表現には曖昧な慣用句が使用」され,境界領域が不分明であることから(片岡〔12〕, p. 50),中世以来,海村同士の紛争がさまざまに引き起こされた。紛争はしばしば暴力/ 武力を伴い,境界侵犯の報復措置として,「海の場合