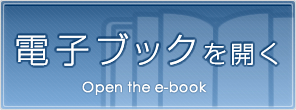100号 page 206/242
このページは 100号 の電子ブックに掲載されている206ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
204 高知論叢 第100号と言うことができる。 全体として言えることは,本書は内外の主要なヒューム研究のなかで,ヒュームの「両義性」,つまり二元的社会認識という最も特色ある視点を強調し,それを最も包括的に....
204 高知論叢 第100号と言うことができる。 全体として言えることは,本書は内外の主要なヒューム研究のなかで,ヒュームの「両義性」,つまり二元的社会認識という最も特色ある視点を強調し,それを最も包括的に捉えようとしたヒューム研究である。本書は内外のヒューム研究史上,こうした特色をもつ最新の研究と言えるであろう。 本書はわが国に限定しても,優れてヒュームへの社会科学的アプローチによる研究伝統を継承しつつ,ごく最近の坂本達哉,犬塚 元両氏の研究以来のきわめて新しいヒューム研究であることは確かである。政治・経済・財政・軍事等に関するヒュームの思想に関心をもつ研究者にとって不可欠な重要文献と言える。 最後に気付いたことを簡単に述べて終ることにしたい。既に述べたように,本書の最大の特色であり,メリットは「両義性」という視点からする,正義と統治をめぐるヒュームの社会認識の分析にある。 ところで「両義性」という言葉はアンビヴァレンスを意味しており,このアンビヴァレンスを基本視角にして,本書ではヒュームの思想の「より包括的な解釈の提示」(p. 9)が試みられた。 そこで気になるのは,このようにヒュームの人間・社会認識の両義性,アンビヴァレンスがここまで首尾一貫して指摘され,それがヒュームの議論のかなめをなすと特に強調されすぎると,議論が余りにも格一的な性質を帯びることになりはしないかといった一種の反発も聞えてきそうに思われる。というのは,両義性と言っても,それは必ずしも格一的なものではなく,両義性のもつ重み4 4は,その内容により同じではないと思われるからである。 ヒュームの二元論的社会認識そのものを否定するのではない。これは欠かせない。それを認めたうえでなお,ヒューム自身の発言には,そのとき,その場合によって彼が一つのことに力点4 4 をおいて主張しようとしたことが含まれていたのではなかろうか。ヒュームが生きた時代のヨーロッパを背景に,彼の発言の力点はどこにおかれたのであろうか。たとえば,近代社会とそれ以前の社会との比較に関するヒュームの認識は,「両義性」の観点からみてどのように論じられるのであろうか。さらに進んだきめ細かな考察に期待したい。