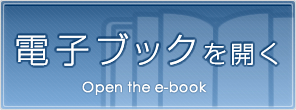100号 page 208/242
このページは 100号 の電子ブックに掲載されている208ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
206 高知論叢 第100号るし,チャレンジしてみたい新しい研究領域や課題も次から次に生まれている。 国際金融システムの方法論に基づいて現実を分析する現代国際金融システム論はまったく手つかずのままであるし,....
206 高知論叢 第100号るし,チャレンジしてみたい新しい研究領域や課題も次から次に生まれている。 国際金融システムの方法論に基づいて現実を分析する現代国際金融システム論はまったく手つかずのままであるし,金融の公共性研究についての現代的課題とその実践方法の研究もこれからの課題である。 細々と年金生活をしながら,たっぷり与えられたぜいたくな時間を使って,これらの課題に挑戦しようと,今から楽しみでうずうずしている。 以下,細かい日付は忘れてしまったので,印象深かったことを覚えているままに,ざっとふりかえってみたい。学生を知る わたしは,1982年に京都大学大学院経済学研究科博士課程を満期終了して,高知大学人文学部経済学科(1998年に改組後は社会経済学科)に常勤講師として着任し,専門科目「国際金融論」と専門ゼミおよび全学の教養教育である共通教育などを担当することになった。 その頃の経済学科は,和気あいあいとした雰囲気があり,談話室に教員が集まっては談笑していることが多かった。教育上の話題も多かったので,そこがざっくばらんな教育方法経験交流会のようなサロンにもなっていた。 京都大学大学院の先輩である松永健二さんとは,この談話室で気楽に話し合うことが多かった。松永健二さんは,その後,共通教育の主幹や人文学部の学部長を歴任され,大学法人化後は高知大学の理事(教育担当)として活躍された方である。 私が高知大学へ着任してまだ右も左もわからないとき,どのように教育や講義をすればいいのかいろいろ迷ったときは,このサロンでのざっくばらんな語らいが大いに役立ち,それによって救われたことが多かった。 後にわたしが全学の共通教育自己点検評価委員会委員長になったときの年度報告書で,「教育経験交流会」を全学に向けて提言したのも,このときの経験を踏まえてのことである。 このサロンで,実は大きなショックを受けることがあった。それは,松永健