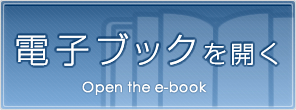100号 page 209/242
このページは 100号 の電子ブックに掲載されている209ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
高知大学での教育活動をふりかえって207二さんの奥様の松永佳子さんについてである。彼女も京都大学大学院の先輩であり,高知大学の共通教育や専門の非常勤講師をしておられた。ショックだったというのは,健二さん....
高知大学での教育活動をふりかえって207二さんの奥様の松永佳子さんについてである。彼女も京都大学大学院の先輩であり,高知大学の共通教育や専門の非常勤講師をしておられた。ショックだったというのは,健二さんからの話を通じて,彼女が非常勤講師でありながらも,高知大学の学生の現状やカリキュラムに対する不満,問題点などを,実に詳細にご存知だったことである。常勤の教師である私がまずもって理解しておくべきことを詳しく知っておられて,驚いた。わたしはそういうことをあまり知らない自分をたいへんに恥じた。 そして何かその秘密があるだろうからそれを盗もうと考えて,夫の健二さんとの談笑からそれをかぎつけようとした。そしてようやくにしてその秘密をつかんだ。 佳子さんは,こまめに学生にアンケートを実施して,問題点を詳細に把握されていたのである。このことを健二さんからうまく聞き出して,わたしはさっそく実行に移した。 アンケート項目は,次の表にあるように考えた。この内容はそのとき以来,ずっと変更せずに使ってきた。データとして継続的に集め,自分の講義や高知大学での教育や環境の改善に向けての基礎資料にしたかったからである。 このアンケートを人文学部経済学科(社会経済学科)の専門科目「国際金融論」と全学対象の共通教育「国際金融と市民生活」で,講義が始まる最初の時間にはかならず配布して記入してもらい回収し,目を通した。また最近,新たに担当するようになった専門教育「金融論」でも同様のアンケートを実施してきた。もちろん匿名アンケートである。当初は,B4用紙の表に印刷してきたが,その内,A4 用紙の表・裏に印刷するようになった。 やってみると実によく理解できた。学生教育は学生の立場にたち,その現状をつかむことから始まるのである。この方法を毎学期,講義の最初に実施することによって,「教育サービスの消費者の立場からみること,知ること」の重要性を教えられた。この消費者の目線で改革するという方法は,その後のわたしの教育改革の基本を貫くものとなった。また研究における私のライフワークである金融の公共性論にも影響を与えた。 ?のアンケート項目については,学生の殺到する人気講義を抽選ではずれて