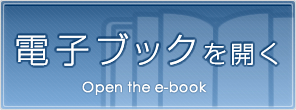100号 page 213/242
このページは 100号 の電子ブックに掲載されている213ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
高知大学での教育活動をふりかえって211で学生の意見や質問,要望を聞くための出席・意見カードの作成へと進んだ。そのきっかけとなったエピソードについて,次に述べてみよう。出席はとるべきか,とるべきでないの....
高知大学での教育活動をふりかえって211で学生の意見や質問,要望を聞くための出席・意見カードの作成へと進んだ。そのきっかけとなったエピソードについて,次に述べてみよう。出席はとるべきか,とるべきでないのか 若いとき,といっても着任からそれほど時間は経っていなかったと記憶しているが,上で述べた談話室での語らいの際に,講義において出席をとるべきか,とるべきでないのか,という事で松永健二さんと意見が異なった。 松永健二さんいわく,「すぐれた授業は学生が来る。おもしろくもない授業を聞かされる学生はたまらない。学生の出席が悪ければ,授業を改革してより多くの学生を来させるよう努力するインセンティブが働く。出席はとらなくてもいい」。実際に松永佳子さんの講義は,出席をとらなくても毎回たいへん多くの学生を集めていたからであり,松永健二さんも人気授業であった。 だが私は出席はとるべきであるとの立場をとった。本音のところ,まだ若くて自分の授業に自信がもてなかったからである。まずは学生に来てもらわないと,そもそも自分の授業改善にもならない。授業にこない学生が自分で勉強しているとは考えにくい。嫌でも来てもらって授業を聞き,そこで一つでも二つでも有意義なことや知識を持ち帰ってもらいたいと,念願したからである。 そうは言ってみたものの,しかし困った。その頃も150名は優にこえる大教室での講義である。どのように出席を取るか迷った。一人ずつ読み上げていたのでは時間が足りない。出席表を回す方法や白紙の紙を配布して氏名を記入させ回収している教師もいるとは聞いていた。しかし何かもっと効率的な方法はないものかと考えた。 そこで当時,知的整理術として流行っていた厚手のカード用紙を使うことにした。最初の授業でそれを配布し,自分の学生番号と氏名を書いてもらう。それを回収して,浅い段ボール箱に仕切りを作り,そこに学生番号順に並べたのである。学生は,タイムカードのようにして,講義に出てきたらそのカードを取り,講義終了時に回収箱の中に入れるのである。 この方式は思わぬうれしい副産物を生み出した。ある時,学生が講義につい