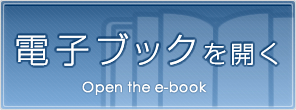100号 page 214/242
このページは 100号 の電子ブックに掲載されている214ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
212 高知論叢 第100号ての質問や疑問をメモにして,そのカードにクリップで挟んで提出することが度々あった。読んでみるとこれが実に面白い。そのメモの内容が面白くて,次回の講義の最初の10分間ぐらいでその質問....
212 高知論叢 第100号ての質問や疑問をメモにして,そのカードにクリップで挟んで提出することが度々あった。読んでみるとこれが実に面白い。そのメモの内容が面白くて,次回の講義の最初の10分間ぐらいでその質問や疑問を紹介して回答をした。その内に,ますますメモの内容を読むのが楽しくなってきたし,学生への回答も好評であったので,これを推奨するためすべてのカードにクリップを付けておくことにした。 そうこうする内,次第に単なる出席をとるという目的よりも,学生からの質問や意見,疑問,要望を聞き取る手段としての目的を基本において,出席カードを改良してみたいと考えるようになった。そしてこの目的をメインにした出席・意見カードを作成してみることにした。B5 用紙を半分切りにした紙の表に,学生番号と氏名を書いてもらい,裏に,質問や意見,疑問を書いてもらうのである。パソコンの普及とともにそれを使って,講義番号と日付,学生番号と氏名を空白にした用紙を印刷・カットして配布し,記入後に回収箱に入れてもらう方法をとるようになった。 毎回,このようなカードを教室の前の机の上に置いておき,授業に出てきた学生は資料とともに,それを1枚とって,講義終了後に書き入れ,回収箱に投入して私に提出するのである。次回の講義の最初の10分間ぐらいで,これらの学生の意見のいくつかを紹介したり,重要な質問・疑問についてていねいに回答をした。 意見カードからわかったことは,これぐらいは常識的に知っているだろうという事や用語で学生が知らなかったことが実に多いことである。初歩的なことでもこの説明から始めないと先に進めない。よくわからなかったことや疑問点については,次回にもう一度ちがう方法か,わかりやすくかみくだいた方法で教え直すようにした。板書の書き方も変え,改善してみたりした。2度目の説明でようやく完全にわかったとか,前回の考え違いに気づいたとの意見カードは多い。このような地道な作業が私の教育能力を高めたことは間違いない。 学生の疑問点に答える内に,研究の重要なアイディアを思い付いたこともしばしばあった。私が知らなかったことを学生から教えてもらったこともある。学生にわかりやすく説明する方法を考える内に,そもそも自分がわかっていな