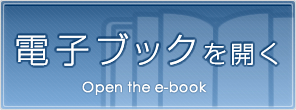100号 page 218/242
このページは 100号 の電子ブックに掲載されている218ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
216 高知論叢 第100号とへの不満は多い。出席もとらずレジュメや資料も配付せず,ただ一方的にしゃべるだけのジコマン講義にその不満は根強い。1回のペーパーテストでは,学生の学習努力や成果を総合的に判断でき....
216 高知論叢 第100号とへの不満は多い。出席もとらずレジュメや資料も配付せず,ただ一方的にしゃべるだけのジコマン講義にその不満は根強い。1回のペーパーテストでは,学生の学習努力や成果を総合的に判断できないのである。 学期終了後,このカードを名寄せし,名前ごとにホッチキスでとじて出席数と意見点数を計算し,レポートと試験結果を加え,パソコンに入力する。これらの作業は毎回大変で,妻や娘にも手伝ってもらったりして乗り切ってきたが,しんどくて何度も止めようと思った。しかし,一度始めた以上は最後までやり遂げようとその度に気持ちを改め,とうとう最後まで続けることができた。協力してくれた家族に感謝する次第である。 わたしは最初の講義において,次の三つの講義方針を大きく板書して説明し,学生の意識変革を促すようにしている。 (1)努力が報われる講義 (2)対話型講義(コミュニケーション型講義) (3)モラル・マナーを守る講義 このようなわたしの講義方法は,今ふり返ってみると,そのきっかけもふくめて学生から教えられたことが基本になっている。わたしの講義を聴いていろんな意見を寄こしてくれた高知大学の学生さんに,心から感謝を表明するものである。 わたしが取り組んできた対話型授業は意見カードを通した間接型であるが,昨年NHK 教育テレビが放映したハーバード大学のマイケル・サンデル教授の「ハーバード白熱教室」は教員と学生が直接に対話・討論するものであった。これに触発され,直接対話型講義をしてみたいと学生に提案したが,消極的意見が多くてあきらめた。高知大生はおとなしいのかなと思っていたが,昨年11月に放映された「白熱教室Japan」をみると,グループ発表というスタイルでおとなしいものであったので,安心をした。子供のときから自分独自の意見をもつよう教育されているアメリカを見習って,日本における管理教育の体系から見直す必要があるだろう。 以上に述べてきた取組みの成果もあってか,2004年には,共通教育自己点検評価委員会が,「学生による授業評価アンケートで評価の高い授業の紹介」としてわたしの講義を取り上げ,その経験を紹介するようにとの依頼があった。