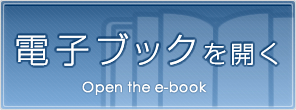100号 page 220/242
このページは 100号 の電子ブックに掲載されている220ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
218 高知論叢 第100号 毎回学生による授業評価を実施,①分かりやすい,②興味深い,③退屈しない,④板書がうまい,⑤理解できた,この五つの基準。A, B, C, ? のいずれかに○をつける方式。教員も授業の開始時間....
218 高知論叢 第100号 毎回学生による授業評価を実施,①分かりやすい,②興味深い,③退屈しない,④板書がうまい,⑤理解できた,この五つの基準。A, B, C, ? のいずれかに○をつける方式。教員も授業の開始時間と終了時間を守る 学生に求めるから教員もモラルを守る。遅く来て授業を延ばす教員に,学生は強い不満。どのように努力すれば良い成績がとれるのかを分かりやすく示す どれをどのように学習すればよいのかを明快・具体的に示し,努力意欲を高めてもらう。実際の生活に役立つ金融と国際金融知識 専門分野以外でも有益な情報をコツコツと収集して授業に活かす。(出所:高知大学共通教育自己点検評価委員会『「学生による授業評価」報告書』2005年3月, p. 29。)教科書教示型か,課題探求型か 経済学科では1回生向けの少人数ゼミ授業「社会科学演習」の方法について,担当教員のそれぞれのやり方やうまくいった方法,問題点などの経験を報告する交流会が,学科教育委員会の主催の下に学科会議で年に一から二回定期的に開催されていた。つい最近になってから,教育方法についての意見交流や開発などの取組みを,FD(Faculty Development)などという難解な言葉で表現して推奨するようになったが,わたしが着任した頃のずっと以前から,経済学科では伝統的にこのような演習(ゼミ)授業の経験や意見交流が定期的に実施されていたのである。 学科教育委員会が活性化していた2000年頃には,3・4年生時の専門演習(専門ゼミ)についても,経験交流会をするということになった。これは画期的なことであった。これまで専門ゼミは誰がどのようなゼミをしているのか,まったくわからない蛸壺状況(ブラックボックス)だったからである。わたしはぜひ知りたいと期待した。 このゼミ教育経験交流会のあとで,飯國芳明教授と感想を述べ合いながら雑談をしていて,ゼミ授業を「教科書教示型」と「課題探求型」に分類できるの