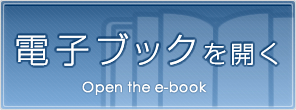100号 page 222/242
このページは 100号 の電子ブックに掲載されている222ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
220 高知論叢 第100号した全学FDが開催されるまでになっている。課題探求型のゼミでは,学生が元気で活発であるので,学習モチベーションが高いことは間違いない。確かに,地域や環境問題などの身近なテーマにつ....
220 高知論叢 第100号した全学FDが開催されるまでになっている。課題探求型のゼミでは,学生が元気で活発であるので,学習モチベーションが高いことは間違いない。確かに,地域や環境問題などの身近なテーマについては,この方法はなじみやすい。 しかし,学生の生活感覚が希薄であり,いわば敷居が高い分野である金融や国際金融について,どのような課題探求型の授業方法を開発すればよいのか,これが私の悩みであって,ずっと模索を続けてきた。そしてようやく今回,一つの方向性を見出し,その試行に踏み切ったのである。ゼミ・シラバスに厳しいことを書いたらゼミ応募者が激減し,調査の適正人数になったことも好機となった。 なお上で対立と述べたが,課題探求型で学習意欲を刺激された学生が,教科書をより深く学ぶ必要性を痛感するようになるので,対立という表現は不適切である。いずれの方法も必要であるが,いずれから始めた方が学習モチベーションを刺激し,より教育効果が高くなるのかという対立である。ただ,両方を統一させるだけの時間的余裕がないのが,もう一つの悩みである。今回の試行で学生・教員ともに学習効果を実感できれば,今後も改良しつつこの調査活動を継続するつもりである。」(出所:末尾の報告書一覧①,注記,pp. 60~61。) 例年,わたしの3年生ゼミでは4月から5月にかけては,日本経済新聞社主催の学生対抗円ドル・ダービー(1ヶ月後の東京外国為替市場の円相場の終値を2回予測するというコンテスト)に参加してきた。2年連続してランキング10位以内に入るという成果はあったが,ますます投機色を強めている為替相場では,新聞の為替欄を読む経験をするぐらいしか学習効果はない。 6月から夏ゼミ合宿と翌年の春休みをふくめて3年生時いっぱいを使って,課題探求型ゼミを試行してみることにした。 さて,何をどうすればいいかである。いろいろ迷ったが,やはり現地調査(フィールドワーク)が基本になるだろうと考えた。金融における現地調査となると,実際に営業している金融機関が対象になるだろうから,それらの金融機関の調査と評価をしてみたらどうだろうかと,ひらめいた。では,何を調査し