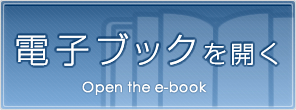100号 page 224/242
このページは 100号 の電子ブックに掲載されている224ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
222 高知論叢 第100号(3)これらの学習と調査活動を通じて,学習モチベーションを高めるとともに,ビジネス・コミュニケーションとビジネス・モラルについて意識を強め,社会的自立に向けた準備トレーニングとする....
222 高知論叢 第100号(3)これらの学習と調査活動を通じて,学習モチベーションを高めるとともに,ビジネス・コミュニケーションとビジネス・モラルについて意識を強め,社会的自立に向けた準備トレーニングとすること。 第1の意義と目的は,金融消費者保護体制の現状を調べることである。 日本版金融ビッグバンと最近の証券仲介業の解禁で,われわれの身の回りにはリスク金融商品が満ちあふれるようになった。ところが日本においては金融消費者保護体制はたいへんに不十分なままである。その結果,金融消費者の被害や金融機関とのトラブルが多数報告されるようになっている。 金融ビッグバンの先進国である英国では,金融ビッグバンの施行とともに,金融サービス法を制定し金融消費者保護の体制もかためた。その後もブレア政権の下で,その改善をすすめている。しかし日本においては,金融ビッグバンが実施に移されてもなお日本版金融サービス法は未確立であった。そしてそれ以降3年も遅れて,2001年4月にようやく金融商品販売法が施行されたのであるが,その内容はお粗末なものであった。 金融商品販売法は,金融機関に金融商品のリスクを説明する義務を課し,元本割れを損害額として認定して個人の立証負担を軽減するという点で前進があったが,他方では,立証責任は消費者の側に残され,英国のPIA オンブズマンのように金融機関に損害賠償を命ずる権限をもった消費者保護の第三者機関の設立が見送られた。また金融商品の勧誘・販売における適合性の原則(運用ニーズや目的に応じた金融商品を紹介・勧誘・販売すること)は,金融機関がその勧誘・販売方針を策定・公表させるだけにとどまった。金融消費者は時間と費用のかかる司法救済に頼らざるを得なく,以前として不利な立場におかれている。 このような状況にあっては,金融機関による適切なリスク説明が,金融消費者保護の重要な役割を担わざるをえない。 はたして金融機関がこの金融商品のリスク説明義務を適切に果たしているのか,このことを調べるためにリスク金融商品の代表格である外貨建金融商品の販売状況を調査してみたいのである。 第2の意義と目的は,学生諸君が金融商品やそのリスクについて知識と理