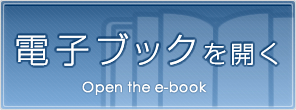100号 page 226/242
このページは 100号 の電子ブックに掲載されている226ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
224 高知論叢 第100号 金融教育への取り組みがいろんな分野で活発になっている。日銀が事務局を務める金融広報中央委員会が「金融教育ガイドブック」を作成した。さらに金融教育フェスティバルの開催や金融教育の....
224 高知論叢 第100号 金融教育への取り組みがいろんな分野で活発になっている。日銀が事務局を務める金融広報中央委員会が「金融教育ガイドブック」を作成した。さらに金融教育フェスティバルの開催や金融教育の公開授業をリレー展開するという。また金融庁でも金融経済教育有識者懇談会を設けたり,小中学生を招いて金融模擬裁判を開くなどしたという。 金融機関と大学の提携も盛んになった。野村ホールディングスなど大手金融機関六社が,東大に設立された「金融教育研究センター」の運営に加わった。さらに野村ホールディングスは学習研究社と共同で金融経済教科書を制作して無料で配布するという。監修は,京大の佐和隆光経済研究所所長である。みずほフィナンシャルグループは,東京学芸大学と金融教育に関する共同研究を始めた。 金融業界においても,米シティグループのように金融教育用のゲーム教材を開発して無料配布を始めたり,社会的責任(CSR)活動と銘打って,経営者を講師として中学校などに派遣している大手銀行もある。 これらの動きは望ましいことである。リスク金融商品があふれかえり,多種多様な金融機関や代理業者が現れており,これにより金融消費者が思わぬ損失を抱え込まされるなどの,金融消費者と金融機関のトラブルが多発しているからである。 しかし,金融機関や金融業界が,心底,金融消費者のために活動しているとは思えない。どうしても疑いの目でみてしまう。 来年度の夏に施行である金融取引法案(当時は投資サービス法案)の議論のさい,金融業界は事務コストの負担を理由に,この消費者保護の規制法案に頑強に反対した。またこんな事もあった。あるときわたしのゼミ生が憤慨してわたしのところへやって来た。聞けば,ある証券会社の寄付講座の講師が,外貨建投資はもうかるぞと,繰り返し強調したというのである。一応配布された資料には為替リスクは書かれたあったというが,あれでは誰でも外貨建はもうかると思って安易な投資に走ってしまうと,ゼミ生は怒ったのである。 先日も講義で,投資信託について私が,「プロにまかせるから安心・信頼できるものではないし,元本保証もなく手数料も高い」と運用実績の資料