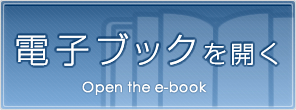100号 page 228/242
このページは 100号 の電子ブックに掲載されている228ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
226 高知論叢 第100号「この研究調査報告書は,高知大学人文学部社会経済学科における専門演習紀国 ゼミに所属する学生(3年生10名)が,ゼミ学習活動として主体的に取り組んだ研究調査活動の成果をまとめたもので....
226 高知論叢 第100号「この研究調査報告書は,高知大学人文学部社会経済学科における専門演習紀国 ゼミに所属する学生(3年生10名)が,ゼミ学習活動として主体的に取り組んだ研究調査活動の成果をまとめたものである。 指導教授である高知大学人文学部教授(金融論・国際金融論)の紀国正典が,学生に提起したこの研究調査活動の意義と目的は,次の三つである。(1)金融機関が金融情報の開示や提供という点で,社会的責任を果たしているかどうか,これを実地に調査・検証してみること。(2)学生みずから自主的に,金融機関の開示情報や提供情報を調査・分析・評価することによって,生きた現実の金融知識を身につけること。(3)就職活動に不可欠な会社研究の方法や技能を学ぶこと。 第1の意義と目的は,金融機関が,ディスクロージャー誌やインターネットのホームページで,金融消費者が必要とする金融情報を十分に開示・提供しているかどうか,そして金融商品や金融にかかわる知識を提供する金融啓もう活動を果たしているかどうか,金融消費者教育にどれほど貢献しているか,これを検証してみることである。 日本版金融ビッグバンの本格化で,金融機関みずから能動的・積極的に,社会や消費者に向けて金融情報を発信しなければならなくなっており,それが重要な社会的責任である時代をむかえている。 競争の自由が拡大して,金融機関は金融消費者にその経営情報を開示・提供し,消費者の選択にゆだねることを求められるようになった。銀行法や証券取引法は,金融機関の経営情報や財務情報を掲載したディスクロージャー誌を,店舗に備え置き公衆が自由に縦覧できるようにすることを定めている。 また,金融商品の開発や参入の自由が拡大して金融機関がいろんな金融商品を取り扱うことができるようになったので,金融商品についての知識やリスクそしてそれらを理解できるための情報を,金融消費者に広く分かりやすく提供する義務が発生した。金融商品販売法は,金融商品のかかえるリスクを消費者に説明することを義務づけている。 金融情報とは,金融にかかわる事柄や事件,指標,認識,知見,知識などを一般的に表す用語であるが,ここでは上記のように,金融機関が金融消費