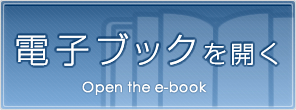100号 page 230/242
このページは 100号 の電子ブックに掲載されている230ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
228 高知論叢 第100号身的に学ぶような教育方法(わたしは教科書教示型の教育方法とよぶ)では得られないことを経験し,自分で工夫する面白さを体感することによって,学習意欲を高めることができるのではないかと....
228 高知論叢 第100号身的に学ぶような教育方法(わたしは教科書教示型の教育方法とよぶ)では得られないことを経験し,自分で工夫する面白さを体感することによって,学習意欲を高めることができるのではないかと考えている。 これらの学習と調査活動を通じて,金融消費者の立場から,より活用できる情報開示や情報提供のあり方について考えることができ,金融機関評価能力をみがくことができる。また学生が金融機関に就職したときには,金融機関の立場から,金融機関にとっての望ましい情報開示と広報活動(IR 活動)について,よりすぐれた方法を提案できる力となるであろう。金融ビッグバンの時代には,この方面の活動の巧拙が,金融機関の経営や信用を大きく左右するのである。 第3の意義と目的は,この調査学習活動をつうじて,就職活動に不可欠で重要な役割をしめる会社研究の方法や技能を学ぶことである。 学生の就職活動を指導するにあたって,これまでいろんな方法を試してきた。その試行錯誤のなかから,もっとも有効で合理的な方法が会社研究であること,しかもこれは学生の弱点でもあることを知った。 自己分析から入ると自分のマイナス面ばかりがみえてきて,自信を失い,先にすすめない。それよりも,実際の会社や自分が希望する会社や業種に関する情報に早くからふれさせ,いったい自分はどのような仕事につきたいのか,これをできるだけ早く考えてもらい,会社という具体的で目にみえる材料と情報を参照して,自分の相性や適性をあれやこれやと探っていった方が,有効で手っ取り早いのである。この調査学習活動で学んだ会社研究の経験や知識が,これからの就職活動に役立つだろうことを期待している。わたしの専門ゼミには金融機関に就職を希望する学生も多いので,おおいに参考になるのではないだろうか。」(出所:末尾報告書一覧②,pp. 29~32。) 第2回目は,高知市に所在する金融機関の顧客勧誘方針の公表状況と内容を調査して,顧客勧誘方針に対する金融機関の社会的責任意識を評価してみることにした(末尾の報告書一覧③参照)。 第3回目は,金融庁がアンケート調査した金融機関の社会的責任活動(金融CSR)の事例をわたしが整理して論文にまとめたので,それを教材として学習