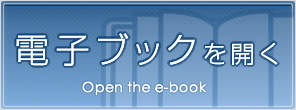高知論叢108号 page 51/136
このページは 高知論叢108号 の電子ブックに掲載されている51ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
行政の判断過程における過誤欠落に関する一考察49査・評価に基づいてなされたか否か,という点に及ぶ,とする9。このようなヴィール判決における司法審査基準は,原子力の安全性に関する司法の実体判断を抑制する趣....
行政の判断過程における過誤欠落に関する一考察49査・評価に基づいてなされたか否か,という点に及ぶ,とする9。このようなヴィール判決における司法審査基準は,原子力の安全性に関する司法の実体判断を抑制する趣旨であることは明らかであるが,その抑制の内実についてはなお,行政権限との緊張関係を含むものであった,とみることができる10。というのは,まず,第二の点である行政のリスク調査・評価義務はかなり厳しく設定されているのに対して,第三の点であるそのチェック方法が「恣意なきリスク調査か否か」というように単純化されているからである。「恣意なき」権力行使とは,連邦憲法裁判所の伝統的理解によれば11,判断の出発点と判断の帰結とがどのようにみても不整合な場合にのみ認められる。すなわち,裁判所は行政の判断過程と決定とを見比べてみて,そのつながりがもっともらしい(plausible)か,あるいは説得力がある(uberzeugend)かをみる審査,いわば,外見的な審査にとどまることになる12。そうすると,このような簡単な審査方法で,科学的見解に接する際,行政に要求される上記の厳格な義務履行がチェックできるのか,という問題が生ずる。加えて,判断余地論の理解の問題もある。判断余地とは法律要件部分に含まれるある一定の不確定法概念の解釈と適用に行政の優先的判断権を認める理論および実務である13。上で挙げた原子力法7 条2 項第3 号の施設設置要件「施設およびその操業によって発生する損害に対して,科学技術的知見に基づく必要な防護措置」というのは明らかに不確定法概念なので,ヴィール判決を普通に読めば,判断余地から行政の優先的判断権を導き出した,と読める14。ところで,伝統的理解では,判断余地論においては,事実認定における裁判所の権9 BVerwGE 72, 300(317).10 ヴィール判決以降の原子力判例の展開についてはDieter Sellner, Atom- undStrahlenschutzrecht in: Eberhard Schmidt-Asmann, u.a.(Hrsg.), Festgabe 50 JahreBundesverwaltungsgericht, Koln 2003, 741?770参照。ただし,本稿は判例の評価を必ずしもこれに従っていない。11 BVerfGE 89, 1, 14.12 Sellner 前掲注(10)749?750.13 赤間・前掲注(4)69頁以下。14 ヴィール判決自身は判決の正当化で直接判断余地については言及してはいないが,その後にヴィール判決をこのように理解する判例がある。BVerwGE 81, 185(190).